Social Impactソーシャルインパクト
Top / Social Impact / 【KAICO】「経口ワクチン」で世界を変える。小さなカイコに注ぐ、大いなる情熱。~九大発スタートアップKAICO株式会社の挑戦~
【KAICO】「経口ワクチン」で世界を変える。小さなカイコに注ぐ、大いなる情熱。~九大発スタートアップKAICO株式会社の挑戦~

カイコで医療を変え、地方における高齢者・障がい者の雇用を生み出し、CO2削減による環境問題にも貢献する。KAICO株式会社は、九州大学で研究されていたカイコからつくるタンパク質の技術をベースに、チャレンジを続ける2018年創業のスタートアップだ。
養蚕業は一般的には役目を終えつつある産業という見方が大半であろう。事実、ピーク時には221万戸あった養蚕農家は、2023年には146戸まで減少し、その数は直近5年の推移だけ見ても3分の1にまで落ち込んでいる(※)。
「当初は勝算などではなく、ただ好奇心だった」そう語るのは創業者の大和氏。その好奇心が使命感に変わり、伝播していくことで今や現実的なビジネスとして成立しつつある。もはや面白い、珍しいだけではない。すなわちKAICOとはどのような会社なのか?大和氏をはじめ「蚕で世界を変えていく。」ことに情熱を注ぐ4氏に話を聞いた。
※出典:農林水産省 資料より
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/attach/pdf/sannshi-10.pdf
大和 建太さん(創業者・代表取締役)
横浜国立大学経営学部卒業。三菱重工業に15年勤務した後、1回目の起業。その後サラリーマンに戻り、九州大学大学院経済学府ビジネススクールでMBAを取得、同大学大学院特任准教授を経て2018年にKAICO株式会社を創業。昆虫カイコでしか出来ないタンパク質で人・動物用の医薬品開発し、世界を変えていくことを目指している。
熊崎 有希さん(最高財務責任者)
大阪大学経済学部を卒業後、地元長崎の地方銀行に就職。働きながら九州大学大学院経済学府ビジネススクールMBAを取得。その後、東京に移住し三菱UFJリサーチ&コンサルティングで経営コンサルタントとして働く。ビジネススクール時代の同期・大和建太氏(KAICO創業者)との縁から、2021年にKAICO株式会社に入社。現在はCFOとして、財務から採用活動までバックオフィス業務全般を切り盛りしている。
藤川 匠さん(品質管理部門マネージャー)
九州大学システム生命科学府システム生命学科を修了後、新卒でアース製薬株式会社に入社。主に家庭用殺虫剤の商品開発、基礎研究等の研究開発業務に従事したのち、海外部門に異動し東アジア、東南アジアでの薬事申請業務に従事。その後 2021 年よりタイ現地子会社に赴任し、現地及び輸出向けの新商品・リニューアルを担当。One Workを介して2024年にKAICO株式会社に入社。品質管理部門のマネージャーとしてKAICOの全商品の品質管理業務を統括する。
福富 拓哉さん(品質管理部門メンバー)
九州大学大学院生物資源環境科学府を修了後、新卒でクラシエ株式会社に入社し、漢方薬の製品開発、品質試験や薬事申請業務に従事。福岡への転居に伴い、2024年にKAICO株式会社に入社。入社後3か月ほどで、品質試験系の立上げを任される、受託開発案件にアサインされるなど、現在すでに中核メンバーとして活躍している。
大和)今日は色々な役割のメンバーに集まってもらいました。それぞれの立場で同じことを考えていることも、違うこともあると思いますので、幅広くKAICOのことを知っていただければ嬉しく思います。
熊崎)普段から言いたいことを言っている環境ですが、実は結構私緊張していて。飾らずお伝えできるようにしたいと思います。
藤川)私も大和さんのようにインタビューは慣れていないので…。でも普段通りお話したいと思います。福富さんは私と直属のラインで、入社1年弱でありながら本音で話せている気がしていますが、まだ知らない一面が見えるのではないかという楽しみもあります。
福富)私も同じ思いでいます。ご期待に応えられるようにいつも以上にぶっちゃけたいと思います。 (一同笑い)
土屋/インタビュアー)是非ぶっちゃけて、ありのままの皆さまをお見せくださればと思います。
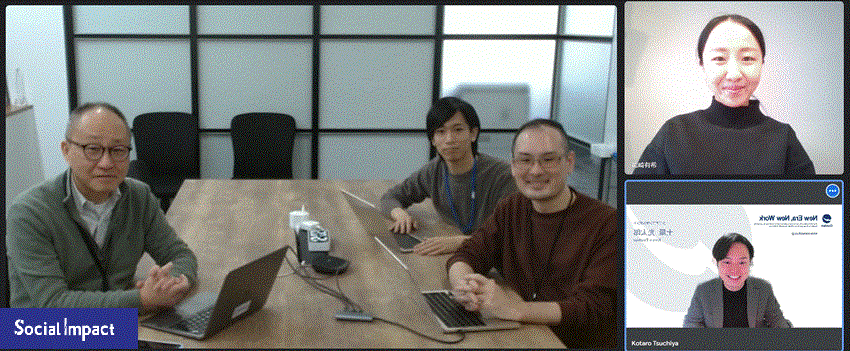
始まりは好奇心だけだった。
「蚕で世界を変えていく。」という情熱と使命感が芽生えるまで。
—カイコの技術に着眼されたきっかけや、会社のなりたちを教えてください—
大和)当社は九州大学で行われていたカイコに関わる研究成果を活かす形で2018年に設立をしました。私自身は三菱重工業株式会社に入社後、15年ほど勤務したのちに別の会社を起業しています。その会社がうまくいかず、サラリーマンに戻ることを決意したものの、やはり再度自分で事業を興したいという思いは持っており、九州大学の社会人向けMBAスクールに通う過程でカイコに出会いました。具体的には産学連携マネジメントという大学の技術を商業化する手法を学ぶ際に、実際に九州大学で研究されているテーマを素材として扱うこととなり、その一つにカイコの研究があったという経緯です。私は文系出身ですのでカイコはおろかバイオ・ライフサイエンスの領域に何ら知見はありませんでしたが、知れば知るほど面白い、最初は面白いという好奇心が勝って教授に「商業化しましょう」という提案をしていました。そこで助成金や大学発スタートアップを支援するプログラム等も紹介してもらいながら約2年会社の設立準備をし、創業に至るという流れです。会社の設立準備、そして実際に設立してしばらくは、カイコからいまのようなビジネスモデルに発展するとは思っておらず、カイコは糸を取るだけではなくて、体を使って有用なタンパク質をつくることができるという事実だけが頼りだったと言っても過言ではありません。製薬会社にアポイントを申し込んでは断られ、論文を読み漁ったり色々な方に相談に乗っていただいたりしながら、実用化、事業化の高いハードルを乗り越えるための兆しを日夜探し続けるという毎日で、精神的にも非常にハードな時期だったと振り返って感じます。
—現在のビジネスに発展していく転機があったのでしょうか—
大和) 転機は2020年のパンデミックです。街から人がいなくなり、大学、自治体、民間企業の活動も全てが変わり、それまでとは異なる発想やアプローチが図らずも求められるようになります。当時テレビ等でも多く報道されていましたので覚えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、ワクチンを開発する上で重要になる『スパイクタンパク質(=Sタンパク質)』というものがあり、当社もそれが作れないかを試行したところ約3か月でつくることができました。その成果を国内外のメーカーに持ち込んだところ、一部の海外製薬会社が興味を持ってくれて「これはチャンスがあるかもしれない」と微かに期待感を持つことができました。一方で、大手製薬メーカーも当然自社でワクチン開発を進めていますので、それができなかったときの選択肢の一つという位置づけに留まり、結果的にメッセンジャーRNAが実用化されたことで日の目を浴びることはありませんでした。ですが確かな一歩として「面白いものがつくれそうなスタートアップがあるんだな」と知っていただくきっかけになったことは間違いありません。そのタイミングで、ノロウイルスの抗原タンパク質を発現させたカイコをそのままマウスに食べさせてみたら、ワクチン効果が出るという実験結果も得られ、製薬メーカーを中心に民間の事業会社との商談も少しずつ機会を増やしていくことができました。
–2020年がターニングポイントだったのですね。そこから現在に至る5年間でどのようにビジネスは変化しているのでしょうか—

大和) 前述のマウスの実験結果ですが、経口ワクチンの可能性が見出されたというのは大きな意味があります。ワクチンはタンパク質ですので、基本的には口から入れるとアミノ酸に分解されてしまい、ワクチン効果が出ないというのが、創薬の世界では一般的な見解でした。それにも関わらず、私たちのカイコは効くというという事実が得られた。意外ではありましたが、物事を進めようとした時に、合理的に導かれた理論どうこうの前に事実を持っていたので、それを切り口として事業会社と一緒に新しいタンパク質をつくって、医薬品に応用できないか。経口ワクチンを普及させることができれば、生活を一変させる一助になるのではないかと考え、当社の中心に据えて伸ばしていこうという決断をしました。注射をするというのは医療従事者にとっても負担ですし、患者さんの目線で見ても病院での順番待ちにつながる一因になります。また、そのような注射型のワクチンも含めてドライカーゴで運搬できない多くの薬品は、手配にあたって冷蔵庫が用意できるかという物理的な制約も受けるのです。コロナワクチンのほとんどはアフリカ諸国に行き届かせることができなかったと言われていますが、本来感染症というのは衛生環境が悪いところで流行するものですので、そういった場所にいち早く届けて、最初に使わないといけません。しかし、冷蔵保管が必要で物流網が未整備な地域には届けられていないのが実情なのです。私たちのつくろうとしている経口ワクチンは、ドライカーゴで運べるという利点があり、それらの問題にも寄与できると考えています。
—「蚕で世界を変えていく。」というミッションにも大きく近づいたのではないかと感じます—

大和) ミッションも7年前からあった訳ではなく、まさに転機となったこの時期に置くことができたもので、今はとてもフィットしていると感じます。現在の事業フェーズとしては、豚の免疫力維持をサポートする飼料添加物をベトナムでの販売を皮切りに普及できそうというところまで来ており、ほかのタンパク質の開発を含めた人向けの医薬品等は、製薬メーカー様と協働を進めているところです。動物向け飼料添加物の事業を中心にご紹介をしますと、注射は動物でも嫌なもので、ギャーギャー泣いたり暴れたりすることも珍しくありません。獣医師にとっても一頭一頭注射を打って回るというのは労力もかかります。日本の就農人口の減少が著しく、新興国においてもホワイトカラーの比率が増えていますので、そのような課題の解決に貢献できるのは喜ばしく思っています。一方で、より広い範囲で当社の技術を活用しようとする際に、日本の養蚕業の衰退が避けられない状況にきていることは制約条件になります。養蚕は桑園の管理、飼育、病虫管理など広い範囲で知識が求められますが、その割に儲からず国内の従事者は数えられるほどまで減少しています。既存の農家さんにご支援をお願いするのは限界がありますので、新しい形の養蚕業の確立が急務と考え、自治体や民間企業にとの連携を進めています。障がいをお持ちの方や高齢者の雇用を通じた経済への貢献、そしてカイコは桑の葉っぱしか食べませんので、飼育ができるのは基本的には桑の木を植えていくための土地がある地方になる。となると過疎化が進む地域の活性にもつながる訳です。トレンドに沿った言い方をすると、これらはサステナビリティな社会の形成に寄与するということなのです。人や動物の病気を予防するために、カイコをたくさん育てる必要が出てきて、仕事が無いとされる過疎化が進む地域においても、ハンディキャップを抱える方の雇用を生み出すことができる。その過程で桑の木を植えることでCO2の削減にもつながります。ビジネスとして採算が合う形で、ステークホルダーの皆さまにも還元できるような形で事業を大きくすることができれば「蚕で世界を変えていく。」というミッションは決して大袈裟なものではないと考えます。
主体者として考え実行することで、機会をつくり、期待を集める。
KAICOのカルチャーと働き方。
—これまで会社の設立から現在に至る変遷を創業者の目線でご説明いただきました。社員という立場から会社をどう見ているのか、数ある選択肢の中でなぜKAICOで働くということを選択されたのかをお聞かせいただきたいと思います—

藤川)私は前職のアース製薬で、研究開発、商品開発に携わっていました。海外転勤を機に働くことやキャリアについて考えるきっかけがあり、自身のやりたいことにもっとフォーカスしてキャリアを積んでいこうと考え、別の道も選択肢として考えることとなりました。大企業かスタートアップかというのはフラットに見ていて、最も優先度が高かったのは大学で学んだタンパク質に関する知識を活かせることです。その一つがKAICOで、ゆかりのある福岡、そして九州大学発スタートアップであることや、私が元々虫好きということで興味が深まっていったというのが入社理由です。
福富)私も大学は九州大学で、クラシエで漢方の商品開発や薬事申請に携わっていました。就職して以降はずっと富山で仕事をしていましたが、家庭の事情で九州に戻る必要が出てその際に選択肢となったのがKAICOです。基本的には製薬会社を中心に検討していた中で、九州を勤務地とする製薬会社の求人のほとんどが工場や生産に関わる業務の一方、KAICOの場合は自身の経験も活かしやすい開発や薬事申請など上流部分のポジションがあり、またそこに課題が大きそうだと感じたことが決め手となりました。
熊崎)大手からスタートアップに転職することに不安は無かったのですか。
藤川)毎月の給与や働き方についての心配は無くて、あるとすれば、大企業ならではの福利厚生や手当など差はあるので少し気になったという程度です。あえてリスクを考えようとすれば出てくるのだと思いますが、飛び込んでみないと分からないことや、自分の行動でリスクを下げられるものもありますので、転職目的に立ち返って「入ってみるか」という感覚で入社を決めました。
—入社前後でギャップを感じたことがあればお聞かせいただけますか—
藤川)ポジティブなギャップという意味になりますが、部署の立上げに近い形で、入社時から品質管理のマネージャーとして会社全体の中での自組織の役割をどう置くか、必要な知識とリソースは何かを定義するという期待をかけてもらったこと。そしてその期待を果たすために様々な方と連携が必要になりますが、社員1人1人の専門性が想像していた以上に高く、早い段階で自分なりに勉強しないとついていけないと感じられたことです。
大和)おかげさまで仕事が増えているタイミングで、藤川さんに仕事が集中してない?
藤川)無理に詰め込まれている感じはなくて、品質管理はKAICOが成長する上で大きく伸びる可能性を感じています。前職よりも視野を広く持って取り組んでいると、やりたいことが自然と増えていくような状況です。他の部門と連携する場面でも、期待以上に反応が返ってくることが多くて、前向きに取り組めています。忙しさという点では、前職でタイに赴任していた時と比べるとそこまで大変ではありませんし、ある程度のプレッシャーがある方が、私はポジティブに仕事ができるタイプだと感じています。

福富)藤川さんのお話を聞いて、KAICOさんの働き方は、想像していたよりもずっと自由なんだなと感じました。私は転職するにあたって、「好きなことをしてお金がもらえるなら、あとは何とかなるだろう」くらいの気持ちでいました。家族も「あなたの好きなようにすればいいんじゃない?」と応援してくれて、それでKAICOさんに飛び込んだんです。ベンチャー企業って、成果を出すためにみんなでガツガツ働くイメージがあって、残業も当たり前だと思っていました。でも実際は、定時で帰る方もいたり、ワークライフバランスを大事にしている方もいたりして、本当に驚きました。
大和)ハードにやりたい人もバランスを取りたい人も活躍できる環境でありたいと考えています。ベンチャー、スタートアップでもステージに左右される部分もあると考えており、今で言えば緩やかに役割分担も階層もできていますので、働き方に対する柔軟性は創業から数年の時代よりも高まっていると思います。また、投資家の皆さまに出資いただいている以上、通過点として上場がありますので、会社として守るべきラインは守るという体制を整備しにいっているところです。
熊崎)特にスタッフ層は時間のキャップがあるという前提で組織運営をお願いしていますので、マネージャーの皆さまは頭を悩ませていることも多いと思います。藤川さんいかがですか。
藤川)確かに、制約があることでマネジメントが難しいと感じる場面もあります。しかし、それを乗り越えるために、生産性を高める別の方法はないか、時間あたりの仕事の質を向上させるにはどうすればいいか、常に問い続けるようにしています。これも、当社が社会に対してより大きな影響を与えていくために必要なステップだと考えています。
—ここでカルチャーについても掘り下げていければと思います。これからどのようなカルチャーを醸成していきたいかという中長期的な話も含めて、御社の組織風土や社員の方の特徴をお聞かせください—
大和)事業の過渡期を経てある程度組織が大きくなった今、改めて組織戦略は描いていかなければいけない時期にきていると思います。後ほどお話する求める人材像にも関わってきますが、自分で目標を見つけて、自分で解決できる方法を探して、自分で実行できる人を常に求めており「蚕で世界を変えていく。」というのは、それこそ医薬品をつくるだけではなくて、様々なアプローチが可能です。ですので、自分が主体者として考えたい、実行したいということを全員が望む企業文化にしていきたいと思います。一方で、そうすると一定の自由度、スタッフ層でも裁量が必要になりますが、どうしても組織としてルールや何らかの線引きをしていかなければいけないタイミングでもあるというのも事実で、そこのバランスにも目を向ける必要があります。それらの事情も踏まえて、根底と言いますか発想の起点としては自主自立、新しいことを創造できるような文化でありたいというのが私の想いです。
熊崎)大きな方向性としては大和さんが仰る通りだと考えています。目指したいカルチャーを醸成していく一歩目として、意見が言いやすいことは必須だと思っており、この点はKAICOの魅力だと感じます。パートさんも含めて職位や社歴に全く関係なく「ここはこうしたい」ということを発信できる環境で、発話し意見交換をすることが会社の成長になり、個人の成長になるということを信じています。これは社員が増えてきても失われていない素敵な風土だと思います。
福富)私も、意見を言いやすい雰囲気だと感じています。実際、私がちょっとした思いつきを話した時も、『じゃあ、それでやってみようか』とすぐに話が進み、実行に移ったことに驚きました。資料を丁寧に作ったり、社内調整に時間がかかったりということもなく、入社したばかりのスタッフの意見にも耳を傾けて、『こういう要素を追加したらどうだろう』とすぐに建設的なアドバイスをもらえるのは、本当にありがたいですね。
藤川)マネージャーだと期待するゴールまでは示されて、やり方はイチから自分で考えることが多いのですが、前例が無い、正解が無いものに対して、周囲の意見を取り入れながら正解を作っていきますので、お互いを尊重しながら対話するというのは大切にしていることです。
—藤川様、福富様の仕事内容、やりがいを感じる瞬間についてお聞かせください—

福富)藤川さんのもとで、品質管理の業務をメインに担当させていただきつつ、研究開発部門の受託開発にも関わらせていただいています。受託開発は、一般的にはあまり知られていない分野ですので、少しご紹介させてください。企業様からいただいたご依頼を形にしていくために、初期の商談からお手伝いさせていただいています。もともと新しいものを開発したいという気持ちで入社し、私自身はカイコでタンパク質をつくるということ自体も初めての経験でした。さらに、受託開発と言っても過去前例が無い新しい分野のご相談も多く、非常にやりがいを感じています。そのために、論文を読んで勉強したり、他部署のレポートを整理したりすることも多いのですが、インプットの質によって開発方針と成果物、つまりはアウトプットの質が大きく変わると実感しており、日々成長を感じています。
藤川)品質管理のマネージャーとして、動物用の経口ワクチンや、AMEDに採択されている人用ノロウイルスワクチンの開発において、品質基準や管理体制などを一から構築する業務に携わらせていただいています。当社には、まだ研究開発が始まったばかりの新しいテーマもたくさんありますので、そちらにも関わらせていただいています。仕事内容そのものに、とてもやりがいを感じており、先日も大和さんから冗談交じりに『実験室に籠っていたよね?』と声をかけていただいたりしました。KAICOの仕事やカルチャーで特に気に入っているのは、一人や自分の部署だけで完結することがないという点です。先ほどのお話にもあったように、議論や対話を重ねながら、みんなで目標に向かって協力し合う日常が、本当に素晴らしいと感じています。
熊崎)お二人が今後やりたいと思っていることはありますか?
福富)やはり人用ノロウイルスワクチン開発に携わりたいです!
大和)今のKAICOにとって非常に重要なテーマですね、福富さんにも是非やってもらいたい。いまはどれくらい関われていますか?
藤川)福富さんは直接のメンバーではないですが、打ち合わせの内容を適宜共有しながらデータ抽出を手伝ってもらっています。
大和)プロジェクトにレギュラーメンバーとして入ってもらってもよいと思う。工数は藤川さんとも相談しつつ進めましょう。
熊崎)このインタビュー中に福富さんへの新たな期待が生まれましたね。手を挙げれば機会が広がっていく、象徴的な事例だと思います。藤川さんはいかがですか。
藤川)個人的には、KAICOの技術を用いてしっかりと利益を生み出せる商品を開発していきたいという気持ちがあります。前職で携わっていた商品の中にはなかなか売れない商品もあり、担当者としては悲しい思いも経験しました。ワクチンに関しては、守らなければならない基準や段階がたくさんあることは承知しております。その中でも、海外のトップメーカーは、チャンスを見つけて一気に市場を獲得するのがとても上手いと感じており、KAICOが、どのように売っていくかという戦略をもっと強化できれば、さらに早く成長できるのではないかと考えています。
大和)うちの看板になるようなヒット商品をそろそろ出したいところ。是非力を貸してください。
KAICOでともに働く仲間との交流が、成長の糧になる。
—好奇心を持ちチャレンジすることを推奨し、社員の皆さまもその組織風土を楽しんでいる光景がよくイメージできました。先ほど大和様にお聞きした、こういった方と一緒に働きたいということや、こんな経験やマインドを持つ方に来て欲しいというイメージがあればお三方のご意見をお聞かせください—

熊崎)藤川さんの感覚が私も近く、チームで働けること、仲間と働くことが好きな方は向いていると思います。当社のビジネスを推進する上で社内外との協業は不可欠ですので、周りに協力を求め、自分も周りに協力したいというスタンスを持っていることが重要ではないかと思います。私は入社する前まで研究者の方は自分の世界観を邪魔されたくないという方が多いという印象を持っていました。実験室に籠って没入することも必要ですが、それを自己完結せず周囲を巻き込むということも大事なことで、研究者の方ほど建設的な議論や対話を大切にしていると今では感じられています。
藤川)ご自身のやり方や価値観を持っていることはとても良いことで、その上でチームワークも大切にされていると感じます。福富さんは、自身で情報を集めながら、私に意見をくれたる、タイミングよく相談をしてくれるのでとても助かっています。自身の仕事に自信を持っていることは、大歓迎です。そういった方が、周りの方のことも尊重できるからこそ、組織全体のパフォーマンス向上につながるのではないかと感じています。
福富) 新しいことや、まだ何も決まっていないことを進めていくことが多い環境です。誰かが気づいてくれるのを待っていたり、慎重になりすぎたりしていると、なかなか前に進めません。ですから、大まかな方向性だけでも自分で考え、積極的に行動できる方が向いていると思います。
もう一つ、これは私自身への戒めも込めてお話したいのですが、転職されてくる方は、少なからず前職での経験や考え方をお持ちだと思います。それをそのまま持ち込むか、全く持ち込まないかという二択ではなく、今の会社に合ったやり方に柔軟にアレンジできると、より貢献できる幅が広がるのではないでしょうか。
大和)せっかくなので1つ、私から2人に聞きたい。将来どうなりたい?
藤川)会社の成長とともに、自分自身も成長し、そしてまた、それが会社の成長にもつながるような、そんな良い関係を築いていけたら嬉しいです。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、もし退職することになったとしても、KAICOと一緒に何かできることがあれば、力になりたいというのが、率直な気持ちです。
福富)面接でお話させていただいたことと全く同じなのですが、『人生の最期を幸せな気持ちで迎えたい』というのが、私の願いです。
大和)採用面接では、幸せな家庭生活が送りたい、と言っていたよね。一緒に働くまでその真意が分からなくて、(仕事よりも)ワークライフバランスを優先したいのかなという印象を持っていたので、仕事面では正直あまり期待していませんでした(笑)。でも実際は、入社2カ月ぐらいして「仕事はどう?」と聞いたとき、まだまだ(余裕があるので、他の仕事も)いっぱい入りますね、ちょっと余裕ですねと言って、自らどんどん役割を広げてくれた。先ほどもノロウイルスワクチン開発をやりたいと言ってくれたしね。
熊崎)大和さん、当初期待していなかったとは、口が滑りましたね。カットでお願いします(笑)
大和)失礼しました。社長としては嬉しい誤算だったということを言おうとした(笑)
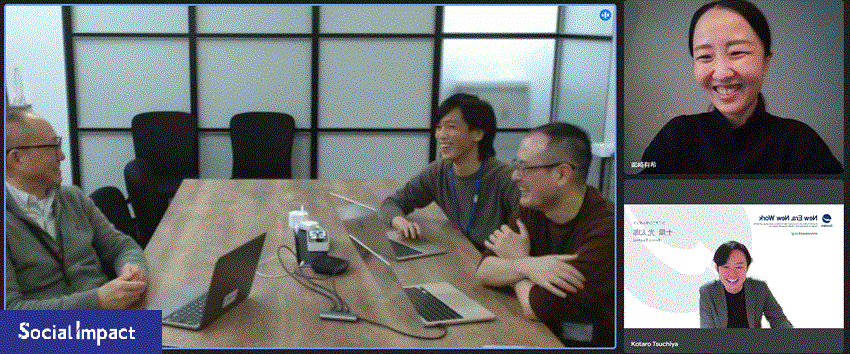
福富)家庭と仕事は、どちらかを犠牲にするものではなく、両立できるものだと考えています。私は、新しいもの創りたいと思っており、これまでの経験から、プレイヤーとして自ら手を動かすことも好きだと感じています。ただ、これはあくまで今の視点から見える範囲での考えです。経験を重ねるうちに、自分の作ったものを世に出したいという気持ちが強くなり、営業の仕事に挑戦したいと思うかもしれません。あるいは、生産技術を極めたいと考え、生産部門で働くことを希望するかもしれません。
そのような機会を制限し、無理のない働き方を選ぶことで、プライベートが充実するとは考えていません。むしろ、様々なことに挑戦できる環境の中でこそ、公私ともに充実した人生を送ることができると信じています。
藤川)福富さんは、実際に自身の仕事が立て込んできそうな時や、残業が続きそうな時には、きちんと報告や相談してくれます。記事を読まれた方は、福富さんが積極的に仕事を引き受けて、とても忙しく働いているイメージを持たれたかもしれませんが、私の目から見ると、確かに仕事熱心ではあるものの、プライベートも大切にしながら、よく考えて働いてもらっていると思います。
—普段のやり取りをリアルに感じることができました。ありがとうございました。今後KAICOへの入社を希望される方に向けて、メッセージをお願いします—
福富)KAICOには、本当に面白い方がたくさんいらっしゃるな、と入社した時からずっと感じています。会社として採用活動をする以上、ある程度似たような考え方や個性を持った方が集まることは、前職の経験からも理解しています。
私が経験してこなかった道や考えもしなかった選択肢を取ってこられた方がKAICOにはたくさんいらっしゃいます。そういった方々と交流することで、自分の考え方や発想が広がる瞬間が本当に多いんです。もし、最近考え方が凝り固まってきているように感じる方や、いつも似たような方とばかり過ごしているなと感じる方がいらっしゃいましたら、ぜひKAICOへの入社を検討いただけたら嬉しいです。
藤川)KAICOは、まずカイコに着目した事業を展開している会社ということで、あまり耳にしたことがない方が多いのではないかと感じています。だからこそ、新しいことに挑戦できる会社だと思いますので、もし今の仕事に少し閉塞感を感じている方にはKAICOは合うのではないかと思います。
社内の雰囲気としては、社員一人ひとりが自己研鑽にとても熱心で、プロフェッショナル意識の高い方が多いと感じています。私も医薬品やワクチンの分野を専門としていたわけではないので、日々新しい知識が増えていくことを実感しています。それは、隣の席の方に質問すれば、期待以上に教えてくれる環境があるからこそだと思います。そういったやり取りを様々な分野で繰り返していくうちに、いつの間にか社内で自分が一番詳しい分野がいくつもできている、なんてこともあるかもしれませんね。
熊崎)バックオフィスを担当する立場として別の角度から。少なくとも大企業と比較するとリスクはあるということは認識を揃えておきたいと思います。この世にないものをつくり出そうとしていますので、販売まで中々進まない、途中でつまずく、対応策が検討されていないトラブルが発生しやり直し、ということが事実起きます。私で言えば資金調達を担当しているので、資金調達が遅延したら今年は採用できない、そうなるとやりたいことが遅れたり、大幅な計画の見直しを求められることになります。それぞれの役割において、プレッシャーを浴びながら「全員が主役」として働いているのがスタートアップだと思います。双方のためにこれを面白い、魅力だと思える人に来ていただきたいと思っていて、共感いただけるなら人生においてお勧めの選択肢ですということをお伝えさせてください。
—最後に大和様からも一言お願いします—
大和)私からお伝えしたいことはたくさん喋らせていただいて、他の3名が補足もしてくれましたので十分だと思います。その上で全員に求めるということではなく、こんな人にも合う会社だよという観点で、将来自分で会社を経営したいという思いのある方も是非ご検討ください。私は既に退職した人も含めて、過去から現在に至るまでKAICOの社員だったという経歴がある人とは少なくとも1回はお話をしている唯一の人間です。創業から数年、全員に必ず面接で聞いていた質問があり、それは「将来自分で会社をつくってやってみたいという希望がありますか」というものです。いまはフェーズも変わってあえて聞くことはしていないのですが、起業するのであれば、今KAICOでやっていることを見て自分が代表ならどうするのか。私も2回独立している起業家の1人ですので、大和の発信や判断はどういった価値観から来ているのか。そんなことを考え、学べるところでもあると思っており、これは今のフェーズでも魅力と感じていただけるのではないかと思います。

ーーー
この記事取材を行った人
エージェント事業部 土屋 光太郎
大学時代にはまちづくりの活動に没頭。全国で行政・企業・大学・地域住民等、多様なセクターの人々を巻き込みながら企画提案・組織運営などを行う。その後、大学院に進み、コミュニティ論を研究し、最優秀賞等の複数賞受賞。
価値の源泉は人だと感じ、2016年リクルートスタッフィングに入社し、求職者の皆様のキャリアに伴走する。また、金融業界(銀行、証券、生保、損保等)を中心に、数名のベンチャー企業から数万人規模の大手企業まで、様々な規模・職種のお客様に対する法人営業に従事。常に200名近くのキャリアに伴走しながら、500名以上の就業機会を創出し、メンバーのマネジメントを行いながら、全社表彰を含め数々の賞を受賞。人材の力を通じて、社会全体を豊かにしたい。という思いからスタートアップ企業の急成長を支援するOne Workに参画。コンサルタントとしてキャリアアドバイジングをメインに活動中。
【保有資格】
キャリアコンサルタント(国家資格)
2級キャリアコンサルティング技能士(国家資格)
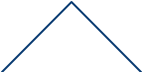 Pagetop
Pagetop
